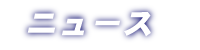 |
| 2010年06月10日 |
| 「エネルギー基本計画」策定、需給構造の抜本的改革目指す |
| 【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:経済産業省、資源エネルギー庁 |
経産省は9日、「2030年の自主エネルギー比率を現在の38%から70%程度まで向上させる」などの目標を盛り込んだ「エネルギー基本計画」第2次改定版を発表した。総合資源エネルギー調査会総合部会(部会長、三村明夫新日鐵会長)が07年の第1次改定以来となる、基本計画の第2次改定案を策定し報告した。 前文で「世界のエネルギー情勢は、資源ナショナリズムの高揚を背景に一段と厳しく、価格も長期的に上昇が見込まれる」、「地球温暖化対策とともに需給構造を低炭素社会型に変革していく必要がある」、「エネルギー・環境分野に対して、経済成長の牽引役としての役割が求められるようになった」との基本認識を示した。 ■2030年に向けた目標 2030年に向けた目標として、以下の5項目の実現を目指すとした。 (1)資源小国である実情を踏まえ、エネルギー安全保障を抜本的に強化するため、自給率(現状:18%)及び化石燃料開発比率(現状:26%)をそれぞれ倍増させる。これにより自主エネルギー比率を約70%(現状:38%)に向上させる。 (2)資源構成に占めるゼロ・エミッション電源(原子力及び再生可能エネルギー由来)の比率(現状:34%)を 約70%(2020年には約50%)とする。 (3)家庭部門のエネルギー消費から発生するCO2を半減させる。 (4)産業部門は、世界最高のエネルギー利用効率を維持・強化する。 (5)わが国に優位性があり今後も市場拡大が見込まれるエネルギー関連製品・システムは、国際市場で最高水準のシェアを維持・獲得する。 ■水素エネルギー社会の実現 新たなエネルギー社会として、CO2を排出しない水素エネルギーを活用した社会システムの構築を目指す。当面は製鉄所からの副生水素など化石燃料由来の水素を活用するが、将来的には非化石エネルギー由来水素の開発・利用を推進する。 また、世界に先駆けて実用化されたわが国の家庭用燃料電池の市場拡大を図る。今後、分散型電源としての利用や業務用など大規模需要への展開を促し、利用効率の向上を図る。 水素充填時間がガソリン並みである燃料電池自動車は2015年からの普及開始に向け、水素ステーションなど供給インフラの整備を推進する。 |
Copyright(C)1999- CHEMNET TOKYOCo.,Ltd

