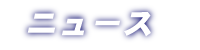 |
| 2015年12月09日 |
| 東大、神経難病が起こる仕組みを解明 |
| 【カテゴリー】:ファインケミカル 【関連企業・団体】:東京大学 |
東京大学大学院の病因・病理学専攻グループ(高柳広教授)は8日、マウスを使った実験で、多発性硬化症において多数の免疫細胞が中枢神経組織に侵入する仕組みを解明したと発表した。 多発性硬化症とは中枢神経系の組織に免疫細胞が侵入して神経を傷つけた結果、視力障害や感覚障害、運動麻痺などの神経症状が起こる自己免疫疾患のこと。 多発性硬化症では病原性のT細胞が産出するRANKL(ランクル)というサイトカインが、中枢神経組織に働きかけてケモカインの放出を促すため、多数の免疫細胞が中枢神経組織に集積し炎症が起きることが分かった。 マウスの多発性硬化症モデルで、RANKLの活性を低下させるような低分子阻害剤が高い治療効果を示すことが分かったことで、今後、RANKLを標的とした新しい治療アプローチの開発が期待される。 同研究成果は12月8日(米国東部時間)、米国科学雑誌「Immunity」オンライン速報版で公開された。 |
Copyright(C)1999- CHEMNET TOKYOCo.,Ltd

