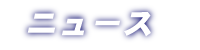 |
| 2024年03月07日 |
| 北大、南海トラフで大量のメタンと水素ガス生成 |
| 【カテゴリー】:原料/樹脂/化成品 【関連企業・団体】:北海道大学 |
北海道大学の鈴木德行名誉教授らの研究グループは6日、南海トラフでフィリピン海プレートと共に沈み込んでいる堆積物(アンダースラスト堆積物)中で、堆積有機物の熱分解によりメタンのほか、水素ガスも主要な天然ガスとして持続的に生成していることを初めて解明したと発表した。 南海トラフや相模トラフの周辺には、主に微生物メタンを含む世界最大級のガスハイドレートや世界最大の生産量を誇る水溶性天然ガス田が分布している。なぜこのように活発な微生物メタンの生成が行われているのかは、これまで不明だった。水素ガスは地下深部での微生物メタンの生成に不可欠だ。 紀伊半島沖の熊野灘付近では、熱分解起源のメタンと水素ガスの生成は過去約220万年間にわたって継続しており、これまでに南海トラフ1kmあたり約5,900億m3/km(日本の年間消費量の約5倍)のメタンを生成し、水素ガスの生成量はそれ以上であることが推定された。フィリピン海プレートの沈み込み帯は、相模トラフから南海トラフ、南西諸島海溝を経て与那国島付近まで約2000kmの距離がある。 今回の発見で、フィリピン海プレートの沈み込み帯における世界最大級の微生物メタン活動に関する理解がさらに深まることが期待される。熱分解起源メタンは同地域での活発なメタン湧出や泥火山の形成に寄与し、深部にメタン溜まりを形成している可能性がある。また、水素ガスが地下深部に貯留されている可能性もある。今後の同地域での資源探査の進展が期待される。 なお本研究成果は国際学術誌「Communications Earth & Environment」(2月21日付)にオンライン公開された。 (詳細) https://www.hokudai.ac.jp/news/pdf/240306_pr.pdf |
Copyright(C)1999- CHEMNET TOKYOCo.,Ltd

