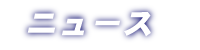 |
| 2024年10月07日 |
| 九大、血液の物性から赤血球の変形能を推定 |
| 【カテゴリー】:ファインケミカル 【関連企業・団体】:九州大学 |
血液中の血球細胞は、約99%が赤血球のため、赤血球の変形能は血液動態を特徴づける重要な物理特性となる。赤血球変形能の低下は動脈硬化などの循環器病と関わる。 九州大学 工学研究院の武石直樹准教授らの研究グループは7日、関西大学、産総研と共同で、実験計測と数値シミュレーションによって、ヒト血液の見かけの粘度から赤血球の変形能(膜せん断弾性率)を推定することに成功したと発表した。さらに、構築した手法は、鎌状赤血球症などに見られる硬化赤血球の膜せん断弾性率の推定にも有効であることがわかった。 本成果により、血液をはじめとする粒子懸濁液のマクロレオロジー特性からミクロ構成要素の変形能の推定が可能なことが示された。本手法論は今後、細胞レベルの新しい血液検査技術や、赤血球の変形能と関わる血中タンパク質量の推定技術に応用されることが期待される。 同研究成果は、米国物理学協会AIP発行の「Journal of Rheology」誌(9月24日付)に掲載された。 <用語の解説> ◆見かけの粘度 :粒子が懸濁した溶液全体の粘度を粒子懸濁前の元の溶液の粘度で除した値のこと。見かけの粘度がせん断速度(ずり速度)に対して一定となる液体をニュートン流体、一定ではない液体を非ニュートン流体という。 ニュースリリース参照 https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/1159 |
Copyright(C)1999- CHEMNET TOKYOCo.,Ltd

